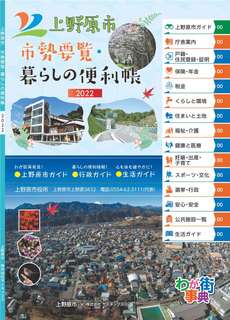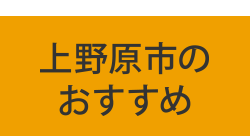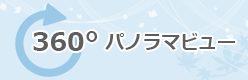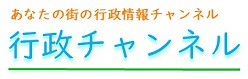本文
上野原市の紹介
こちらから音声読み上げページに移動できます。<外部リンク>
上野原市の概要
上野原市は、山梨県の最東部に位置し、首都圏の中心部から60から70km圏にあります。東は神奈川県相模原市、南は道志村、西は大月市と都留市、北は小菅村と東京都西多摩郡に隣接しています。
市内には、中央自動車道上野原ICと談合坂スマートIC、JR中央本線上野原駅と四方津駅があり、国道20号、主要地方道である四日市場上野原線、上野原あきる野線、上野原丹波山線、そして大月上野原線が通っています。これにより、首都東京を中心とする関東圏から山梨県への重要な交流拠点となっています。
また、地域内を流れる桂川、秋山川、鶴川、仲間川およびそれらの支流が形成した河岸段丘は、住民の生活基盤となっています。山岳や段丘、河川が作り出す自然環境は日照時間が長いなど、さまざまな自然の特徴に恵まれています。なお、桂川と秋山川はともに相模川水系に属し、神奈川県における主要な水道供給源となっています。
面積
170.57平方キロメートル
上野原市全体マップ
気候
気候は内陸的で、夏冬の寒暖差・昼夜の温度差が大きく、 降雨量が少ないため、四季折々の美しい自然環境を生みだしています。
人口と世帯(令和8年2月1日現在)
- 20,717人(男性 10,390人、女性 10,327人)
- 10,026世帯
- 人口の推移については、「人口と世帯」のページをご覧ください。
-
上野原市の市章

美しい自然につつまれ、悠久の歴史と文化を誇る上野原市の「上」をモチーフにしています。
オレンジは「暖かな心」、ブルーは「空と清流」、グリーンは「緑豊かな自然」をイメージしています。
(平成17年10月24日制定)市の歴史
古代律令制における統治体制では、国の下部組織として郡が置かれ、さらにその下に郷がありました。甲斐国(山梨県)には、山梨郡、八代郡、巨摩郡、都留郡の4つの郡が存在し、秋山村および上野原町は都留郡に属していました。
明治時代に入ると、郡区町村編成法や市制町村制の施行等により、明治22年に秋山村が村制を施行、一方、上野原町は、明治時代の初めには20あった村が、明治8年までの合併を経て、昭和の大合併前の8村体制となりました。その後、上野原村の町制施行を経て、昭和30年に8町村が合併し、上野原町が誕生しました。
両町村がそれぞれの歴史を刻む中、平成の大合併が進められ、上野原町・秋山村でも平成15年4月に合併協議会を設置し、新設(対等)合併に向け協議が進められ、平成17年2月13日上野原町と秋山村が合併し「上野原市」が誕生しました。上野原市の花と木と鳥
市の花 りんどう

市の木 山もみじ

市の鳥 うぐいす

上野原市の紹介動画
市勢要覧・暮らしの便利帳