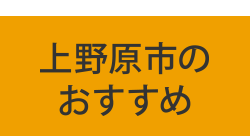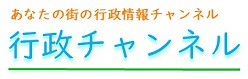本文
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度
対象者
市内に住所がある75歳以上の方。一定の障害のある65歳以上の方(新たに加入される方は申請が必要です。また申請により撤回することも可能です。)
いつから対象になるのか
75歳の誕生日当日からです。手続きは不要です。
一定の障害がある65歳以上の方で、山梨県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、広域連合の認定を受けた日から対象となります。
資格確認書
令和7年度は、後期高齢者医療制度の被保険者にマイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は、7月中に特定記録で郵送されます。この度お送りする「資格確認書」の有効期限は、令和8年7月31日までで、届いた日からお使いいただけます。
マイナ保険証をお持ちの方は、これまで通りマイナンバーカードを医療機関に提示することで、医療にかかることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日から現行の保険証(被保険者証)は新規発行されなくなります。
※令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は、原則、有効期限まで使用可能ですが、負担割合変更、転居などで異動が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。
※令和6年12月2日以降マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>
保険料の決まり方
保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。
保険者の保険料(賦課限度額80万円)=均等割額(50,770円)+所得割額(前年所得-43万円(基礎控除額))×11,11%
※保険料は2年毎に見直され、山梨県内は統一の保険料率となります。
保険料の軽減
所得の低い方の軽減措置
世帯の所得水準にあわせて、均等割額が軽減されます。
軽減割合 |
軽減該当世帯(世帯主と被保険者の総所得金額等により判定) |
|---|---|
7割軽減 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 |
5割軽減 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+30.5万円×被保険者数」 以下の世帯 |
2割軽減 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+56万円×被保険者数」 以下の世帯 |
※基礎控除額などは、税制改正などで今後かわることがあります。
※公的年金を受給されている方は、年金所得からさらに15万円を控除した額で判定します。
健康保険等(社会保険)の被扶養者の軽減措置
後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方は、加入してから24か月までの期間は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。また、上記の基準に応じて5割軽減より高い軽減が該当する場合はより高い軽減割合を適用します。
※国民健康保険及び国民健康保険組合である場合は、対象となりません。
保険料の納め方
保険料の納め方は受給している年金の種類や受給額によって変ります。納め方は以下の通りです。
年金からの差し引き(特別徴収)
対象となる方
年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)
納め方
年6回の年金定期払いの際に、介護保険料と同じ年金から保険料が差し引かれます。
年金からの差し引きの方でも口座振替に変更が可能です
年金からの差し引きで保険料を納める方は、要件を満たした場合に納付方法を口座振替に変更することができます。納付方法を変更する場合は、税務課窓口へお申し出ください。
納付書で各自納付(普通徴収)
対象となる方
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
納め方
市町村から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関で納めます。納期は年8回(7月から2月まで)となります。
口座振替を利用しましょう
保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。次に掲げた必要なものをもって、市指定の金融機関でお申し込みください。
必要なもの
- 保険料の納付書
- 預金通帳
- 通帳の届出印
- 身分証明書等
給付の内容
所得区分について
| 所得区分(自己負担割合) | 所得区分説明 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(3割) |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 |
|
| 一般2(2割) | (1)世帯内に被保険者が1人の場合 「住民税課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」 (2)世帯内に被保険者が2人以上の場合 「世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者 |
|
| 一般1(1割) | 現役並み所得者及び低所得者以外の方 | |
| 低所得者2(1割) | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方 | |
| 低所得者1(1割) |
世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の収入から80万円を控除して計算) |
|
〇負担割合が3割の方でも、次の条件を満たす方は、1割または2割となります。
(1)同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万未満
(2)同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入額合計が520万未満
(3)同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額は383万以上だが、同一世帯の70歳~74歳の方の収入を含めた金額が520万未満
※昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下であること。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められる限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
| 所得区分 | 外来の限度額(個人ごとの限度額) | 外来+入院の限度額(世帯ごとの限度額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉※1 |
|
| 現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉※1 |
|
| 現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※1 |
|
| 一般2 |
令和7年9月まで |
57,600円 〈44,400円〉※1 |
| 一般1 | 18,000円 〈44,400円〉※1 |
57,600円 〈44,400円〉※1 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 15,000円 | |
※1過去12ヶ月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。
※2医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定
限度額までの支払いとする場合には、あらかじめ国保の窓口にて認定証の交付を申請する必要があります。交付された限度区分が併記されている「資格確認書」を医療機関の窓口に提示すると、ひと月の同じ医療機関等の窓口支払いが一定の限度額までとなります。
令和6年12月2日以降は、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の、新規発行は終了しています。
前年度交付を受けている方またはすでに資格確認書への併記申請を行った方で、今年度も引き続き認定された方に対しては、「資格確認書」に限度額の区分が併記されますので、ご確認ください。
入院した時の食事代
低所得者1・2の方が食事等の軽減を受ける場合には、入院の際に限度額が記載されている「資格確認書」の提示が必要になりますので、事前に申請してください。
※低所得者2の方が、過去12ヶ月の入院日数90日を超える場合、90日以上入院していることがわかる医療機関の領収書等を添えて長期入院の申請をしてください。
入院時食事代の標準負担額
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 490円 | |
| 一般 | 490円 | |
| 低所得者2 | 90日までの入院 | 230円 |
| 過去12ヶ月で90日を越える入院 | 180円 | |
| 低所得者1 | 110円 | |
療養病床に入院した時の負担額
療養病床に入院した時の食費と居住費は、決められた負担額以外は、入院時生活療養費として支給されます。
療養病床の標準負担額
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般1・一般2 | 510円※1 | 370円※4 | |
| 低所得者2 | 240円※2 | 370円※4 | |
| 低所得者1 | 140円※3 | 370円※4 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | |
※1一部医療機関では「現役並み所得者」及び「一般」の食費が470円の場合があります。指定難病患者は300円です。
※2医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び、指定難病者は過去12か月間の入院日数90日を超えた際に190円となります。
※3医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病者は110円です。
※4指定難病者は0円です。
高額医療・高額介護合算制度
医療費の自己負担額と介護サービスの利用料が合算できるようになります(高額医療・高額介護合算制度)。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して下記の限度額(年額)を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
高額介護合算療養費の限度額
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円※ |
※介護保険受給者が世帯内に複数いる場合は、医療と介護で限度額が異なります。
その他の給付
上記の他に、葬祭費の支給(5万円)、療養費の支給(補装具等)等があります。