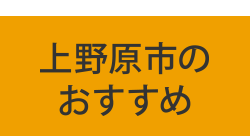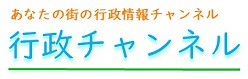本文
国民年金について
対象者と加入する方
日本に居住する20歳以上60歳未満の方には、外国人も含めて国民年金に加入し、保険料を納付することとなっています。
国民年金の加入者は次の3種類に区分されます。
第1号被保険者
日本に居住する20歳以上60歳未満の方で、次の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない方
第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金保険や共済組合に加入の方
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)
手続きについて
次の要件に該当するときは、各種の手続きが必要となります。
※年金の各種手続きにおいて、平成30年3月より原則として個人番号を記入していただくことになりました。手続きをされる際には、個人番号の分かる書類及び本人確認書類(運転免許証など公的機関の発行した写真付きの書類は1種類、保険証や預金通帳など写真付きでない物は2種類)をお持ちください。
また、スマートフォンを利用した電子申請も可能です。事前にマイナンバーカードの取得と、マイナポータルの利用者登録の手続きが必要となりますので、詳細は年金機構ホームページをご覧ください。
20歳になったとき(厚生年金や共済組合の加入者は除く)
20歳になった方には、20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」等の通知をお送りさせていただきます。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」等の通知が届かない場合は、お問い合わせください。
勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)
必要なもの:年金手帳又は基礎年金番号通知書、若しくはマイナンバーカード、退職した年月日のわかる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(配偶者の退職、離婚、死別、収入増など)
必要なもの:年金手帳又は基礎年金番号通知書、若しくはマイナンバーカード、扶養されなくなった年月日のわかる書類
保険料について
毎月の保険料は、翌月の末日まで納付してください。保険料の納付は、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で現金による納付のほか、口座振替またはクレジットカードによる納付方法があります。また、将来の一定期間の保険料を前払いすると、保険料が割引される制度もあります。
保険料の減免制度について
所得が少ない等の理由により、保険料を納付することが困難な場合は、市役所で各種の免除制度等を申請することできます。年金事務所で本人・配偶者・世帯主の所得などを審査し、承認された場合は保険料の全部または一部が免除されます。50歳未満の方は、本人と配偶者の所得で審査される納付猶予制度もあります。
また、対象となる学校に在学し、本人の所得が一定以下の場合、「学生納付特例制度」を申請することができます。承認されると、保険料の納付が猶予されます。
失業等による免除特例
失業等により保険料の納付が困難な場合には、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
必要なもの
・年金手帳又は基礎年金番号通知書、若しくはマイナンバーカード
・勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピーまたはハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピーなど
学生納付特例制度
対象となる学校に在学し、本人の所得が一定以下の場合、「学生納付特例制度」を申請することができます。承認されると、保険料の納付が猶予されます。
必要なもの
・年金手帳又は基礎年金番号通知書、若しくはマイナンバーカード
・在学証明書(原本)または学生証
※学生証の有効期限が切れていると、申請を受け付けることができません。期限が切れていないかご確認の上申請をお願いいたします。
保険料の追納
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金額が低額になります。このためこれらの期間の保険料については、10年以内に追納することにより、年金額を増やすことができます。
※ただし、免除が承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料に一定の加算金が付きます。
関連リンク
年金に関する詳しい内容は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>